よく、「アロマ(精油)はリラックスするためにおすすめ♪」「ストレス軽減に♪」などと言われていますが、香りを嗅ぐだけで本当にそんな効果があるのか?と疑問に思われる方もいらっしゃると思います。
本記事では、アロマインストラクター資格所持&オーストラリアで自然療法を学んだ経験をもとに、アロマが身体に働きかける仕組みについてお伝えさせていただきます。
もし宜しければ最後までご覧ください♪
アロマ(精油)は自律神経系に働きかける
アロマ(精油)のイメージ
アロマ(精油)は一般的に、「ストレス解消」「リラックス」「リフレッシュ」など、気分を変えたり心に働きかけるイメージが強いのではないでしょうか。
そのため、「精神的なものではないか?」「その人の気分次第では…」と思われる方もまだまだいらっしゃると思います。
ですが、アロマの働く仕組みは理論に基づいたものとなっています。
アロマがストレスに働きかける仕組み
さて、「ストレス解消」「リラックス」「リフレッシュ」などをしたい場合、どうすれば良いでしょうか。
手を動かしたい時に手を動かせたり、歩きたい時に歩けたりする動作とは違って、人間の感情に関わる部分の多くは、自分自身でコントロールできないと思います。
怒ろうと思って怒る人、泣こうと思って泣く人、喜びたくて喜ぶ方人は、演技をする人以外にいませんよね。
気づいたら怒っていた、気づいたら悲しい気持ちになっていた、考えるよりも先に笑顔が出ていた…など、自分で次の感情を認識したり予測する前に、既に感情が出ていると思います。
それと同様に、身体にかかるストレスも自分自身ではコントロールできません。
ちなみに、ストレス=悪いストレスだけではありません。
・仕事で昇進した、結婚をした等で環境が変わった→良い刺激
・悲しいことやショックな出来事があった→悪い刺激
上記のように、身体にとって必要なストレスもあります。
また、日々何気なく生活をしていること自体が、様々なストレスがある環境に身を置いていることになります。
では、どのような仕組みでストレスを感じて身体を調整しているのでしょうか?
それには「脳」が大きく関わっています。
脳の中でも、視床下部という場所が、ストレスとなる「快」や「不快」の刺激を感じ取っています。
この視床下部の身体における役割は、「神経系(自律神経)」「内分泌系(ホルモン)」「免疫系」のコントロールです。
適度なストレスであれば、視床下部からの司令で自律神経が調整され、身体のバランスは一定に保たれます。
ですが、過度なストレスがかかったり、長時間緊張状態が続いたりすると自律神経の調整が上手くいかなくなり、密接に関係している内臓機能が低下したり、ホルモンバランスが乱れたり、免疫力が下がって身体に不調が現れてしまいます。
このように、ストレスと自律神経は密接に関わっており、自律神経は意識してコントロールできるものではありません。
その点、アロマ(精油)は視床下部に働きかけ、自律神経や内臓機能、内分泌系・免疫系に作用する力を持っているとされています。
アロマテラピーの仕組み
アロマ(精油)は化学成分で成り立っている
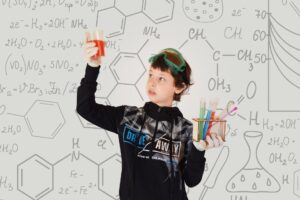
まず、アロマ(精油)は、お花や葉っぱ、樹木などの植物から、様々な方法で芳香(香り)成分を抽出したものです。
抽出された芳香成分は、基本的に化学成分で成り立っています。
例えば、水=H2O、酸素=O2、二酸化炭素=CO2のように、、
目には見えませんが、それぞれ化学構造を持つ、有機化合物となります。
身体への入り方①〜鼻から入って脳に刺激〜
そんな有機化合物であるアロマの代表的な取り入れ方は、「香り(芳香成分)」を嗅ぐ、鼻からの経路です。
この香り(芳香成分)を嗅ぐ=「鼻から精油成分を取り入れる」ことが、視床下部にダイレクトに働きかけることに繋がります。
簡単な流れは以下となります。
①香り(芳香成分)を嗅ぐ=精油成分が鼻から入る
②鼻から入った精油成分は、鼻の奥に広がる鼻腔と呼ばれる空間に入り込み、一部が天井付近の嗅上皮に吸着する
③ニオイを受け取る嗅覚細胞が興奮し、精油成分は電気信号に変換されて嗅神経を介して脳に伝達される
④脳の一部である視床下部に伝わり、自律神経系に影響を及ぼす
以上のように、精油成分は鼻から入ると電気信号に変わって脳(自律神経を司る視床下部)にダイレクトに作用する仕組みとなっています。
この時、鼻から入る(香りを嗅ぐ)精油成分の違い(精油の種類の違い)によって、脳への作用の仕方が変わります。
リラックスさせるのか、リフレッシュさせるのか、ホルモンバランスに働きかけるのかなどの作用は、精油が持つ化学構造の違いによって変わるということです。
身体への入り方②〜肺から入って血流を巡り全身に〜
もう1つは、呼吸による肺からの経路です。
精油の芳香成分(香り)を鼻や口から吸い込むと、気道を通って肺にある肺胞に届きます。
その後血液中に入り全身を巡り、各組織や器官に届く仕組みです。
深呼吸をして香り成分を深く吸い込むと、その分取り入れられる量は増えるため、精油の効果も感じられやすくなります。
肺から取り入れた精油は、約5分後には血液中に確認でき、7〜8分で体外に排出されると言われています。
身体への入り方③〜皮膚から浸透して血流を巡り全身に〜
3つ目の入り方として、「アロマトリートメント」や「フットバス・全身浴」、「オイル塗布」などによる、皮膚からの経路があります。
皮膚に付いた精油成分は、真皮にある毛細血管やリンパ管に入り、全身に循環していきます。
「経皮吸収」とも呼びますが、精油が入ったマッサージオイルは、脂質のため皮膚に馴染みやすく、分子が比較的小さいため細胞の間から浸透しやすいという特徴を持っています。
また、マッサージによる血流促進によってより浸透力が高まる傾向にあります。
塗布後約15〜20分で血液中に確認でき、12時間〜24時間程度身体を巡ります。
※皮膚でパッチテストを行う際は、24〜48時間程様子を見ることをおすすめしています
この皮膚からの吸収によって、例えば腰にオイルを塗布して腰痛を和らげたり、足をマッサージすることでむくみを改善したりと身体の部位により働きかけることができます。
また、トリートメントで触れられることによる「心地よさ」が脳の視床下部に伝わり、神経をリラックスさせることにも繋がります。
なお、塗布する部位の範囲にもよりますが、鼻から芳香成分を取り入れるよりも、身体を巡る精油成分の濃度は高くなる傾向にあります。
そのため、小さいお子様や妊婦さんには、身体への塗布よりも香りを嗅ぐ芳香浴で楽しんでいただくことがおすすめです。
関連:妊娠中にOKなアロマ(精油)って?
まとめ
以上のように、アロマ(精油)は3つの経路で身体に取り入れることができ、「癒される香り」を感じる鼻からの経路では、主に脳の視床下部に働きかけ、自律神経系・内分泌系・免疫系の調整に関与するとされています。
そのため、アロマを嗅いでリラックスしたり、気分転換できるのは気のせいではなく、身体にしっかりと作用されているから、ということになります。
理論上効果があると知るだけで、アロマの取り入れ方が変わってきますね♪
アロマの様々な楽しみ方はこちらの記事でもまとめていますので、ぜひあわせてご覧ください♪
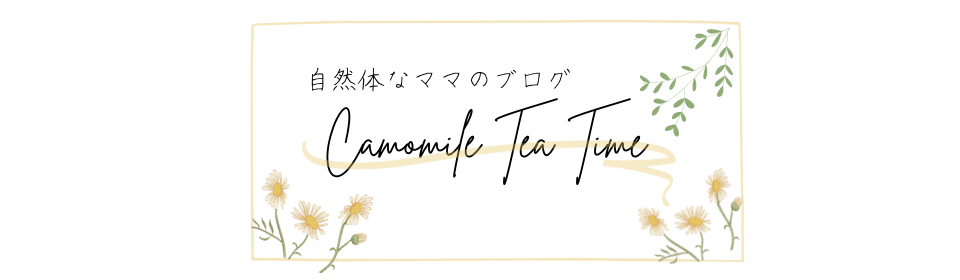



コメント